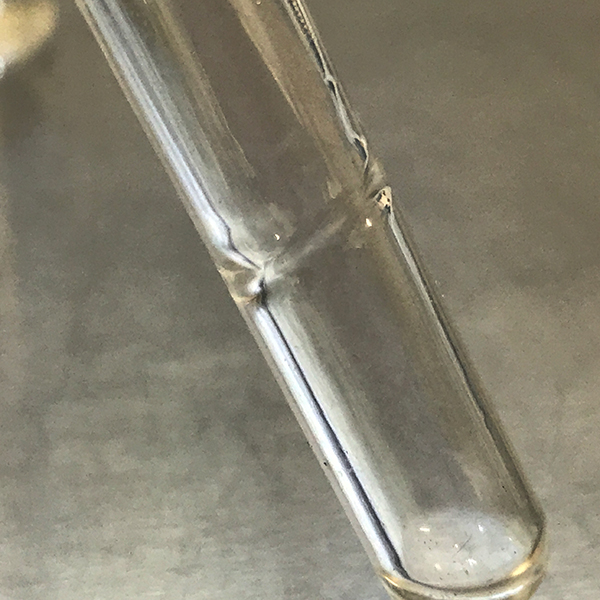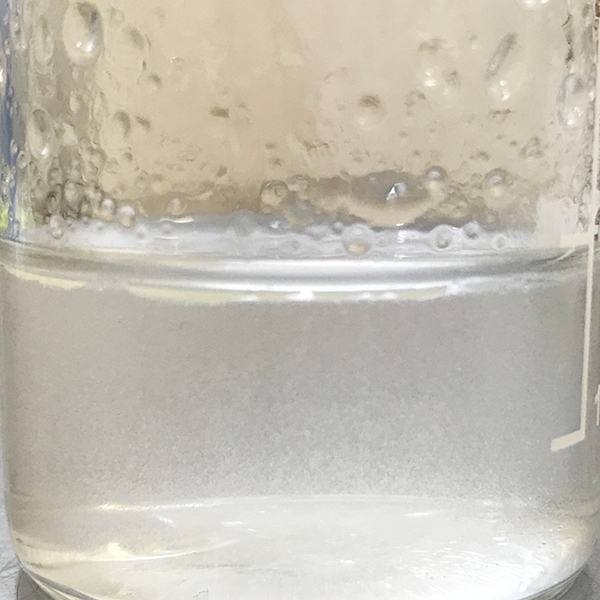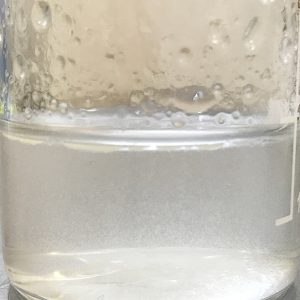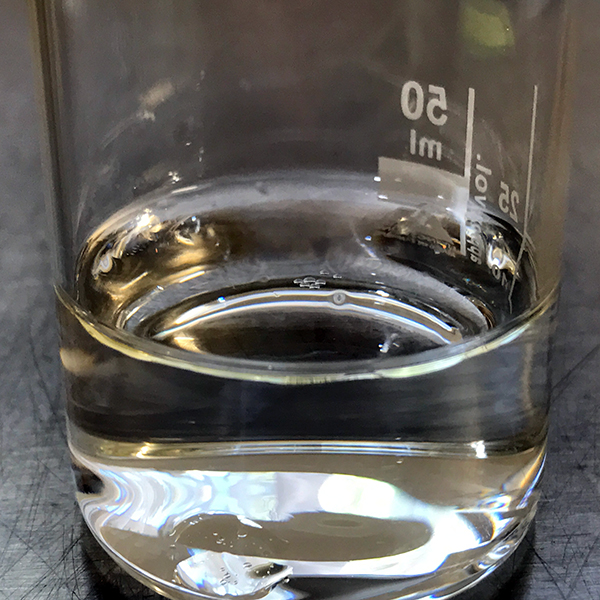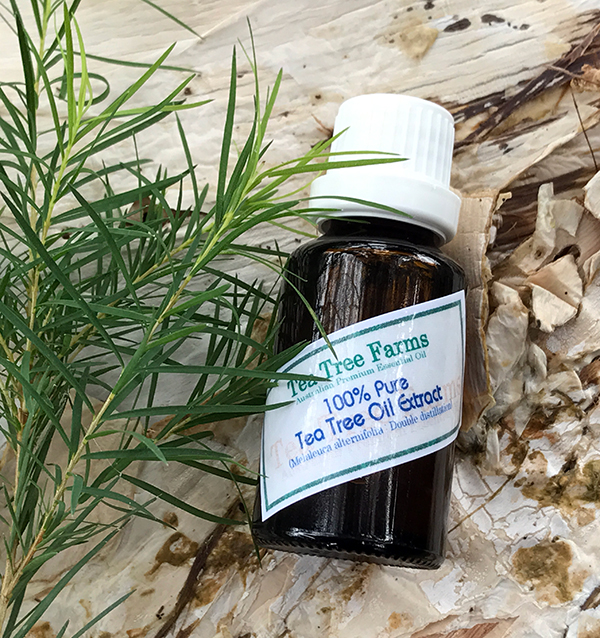レモン果汁を思わせる爽やかで鮮烈な香り。レモンとは全く関係ないオーストラリアの樹木の枝葉から抽出されるこのエッセンシャルオイルはレモンマートルオイルです。その成分構成の90%以上がシトラール成分で構成されているので、その香りはとにかくスッキリしていてパワフルです。
しかし、パワフルゆえに気をつけなければいけないことがあります。それはシトラール成分にる刺激。たとえば高めの濃度で屋内に拡散すると目や粘膜にチクチクと刺激を感じることも。また肌への使用においても、十分に希釈を行わなかった場合には(体質にもよりますが)、発赤や湿疹といった作用が生じる場合があります。
レモンという、とても親しみやすい香りのため手軽に色々なシーンで活用したくなる香りですが、その非常に高いシトラール成分の濃度より、レモンマートルは慎重な取り扱いを求められるオイルでもあるのです。