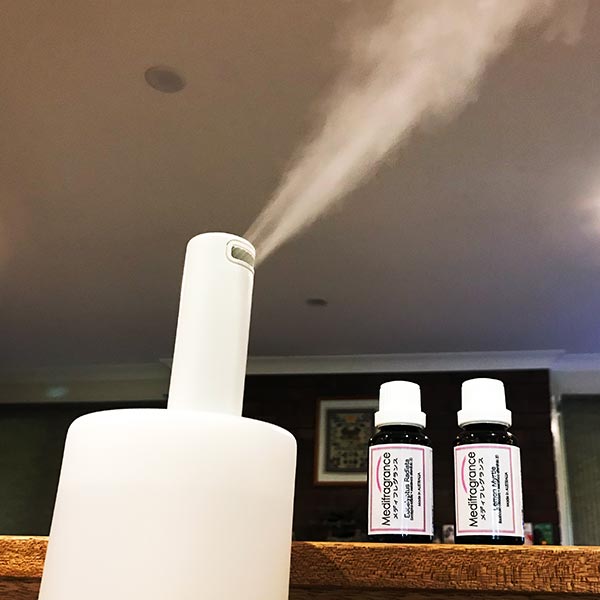ティーツリーオイルにおいて、その含有量が少ないほどに「高いグレード」とされるのが1,8シネオール。刺激成分となり、含有が多いと香りに大きな影響を与えるほか、オイルを肌に使用した際には肌刺激成分として発赤や湿疹等の原因となることが知られている成分です。
お掃除などで活用されることの多い「日用品グレード」の比較的安価なティーツリーオイルに10%などの高い割合で多く含まれる(プレミアムグレードのティーツリーオイルの場合、3%程度しか含まれません)この成分ですが、逆にこの成分を非常に高い濃度で含んでいるエッセンシャルオイルがあります。それはユーカリオイル。
ユーカリには様々な種類があり、そこから抽出されるオイルも成分構成は様々なのですが、この条件に該当するのはグロブルス種、ラディアータ種、ブルーマリー種などが挙げられます。
特にブルーマリー種は1,8シネオールが90%を超える濃度で含まれるため刺激が大変強く、体質によっては素手での取り扱いに注意が必要になるほど。最も生産量の多く一般的なグロブルス種でも80%台含まれます。ラディアータ種では70%台ですので、このレベルであれば香りを楽しむ余裕も出てくるかも。そんなこともあって、この成分は別名「Eucalyptol」とも呼ばれています。
なお、ティーツリーオイルでは嫌われる1,8シネオールですが、刺激の一方で喉や鼻のズグズグを緩和してくれたり、血流を良くすることで筋肉の痛みやうっ血を緩和してくれる効果が知られていて、オーストラリアでは筋肉痛対策の医薬品にこの成分を多く含むユーカリオイルが活用されています。