
一般的なラベンダーオイルにある2つの香りの特徴は、香りの最初に感じられる「ツンとした香り」と、その後に上がって来る「フローラルな香り」の組み合わせです。
前者は油性インクに似たクセのある香りで一般的にあまり好まれるものではなく、結果的にこの香りが抑えられたラベンダーオイルにより高い評価が付き、これが価格に反映されています。
後者はリナロールという成分に由来する、ラベンダーの香りに期待されるフローラルな香りですから、多くの場合でこの香りが強いオイルほど高評価を受ける傾向があります。
たとえば、これらの二つの条件を満たす事で、世界的に高い評価を受けているのがオーストラリア・タスマニア産のラベンダーオイルです。
一方でリナロールには「アレルギーの原因」として知られる側面があります。もちろん毒性があるわけではなく、全ての人に対してアレルギーを誘発するものではありませんので、体質の上で影響を受けない方には全く問題はありません。
このリナロールが体質に合わないという(全体の10%から15%程度と推測されている)方に対しても、影響を与えにくい程度にまでその含有量が少ないのがニュージーランド産のラベンダーオイルです。
オイル製造の段階でリナロールを抜き出したわけではなく、もともとリナロールの含有が少ない特殊なケモタイプのラベンダーから作られたオイル。リナロールが少なくなった分だけ、アレルギー性のない酢酸リナリルという成分の含有が増えていることから、低アレルギー性のラベンダーオイルとして広く認知されるようになりました(詳しい成分構成は公開している成分分析表を参考にしてください)。
その香りは「ツンとした香り」は抑えられていますが、「フローラルな香り」を作る成分の含有が少ないため、全体的に香りはあっさりした仕上がりに。オーストラリア産のラベンダーオイルとは対極的な香りと言えますが、『ラベンダー独特の自己主張』を少し抑えたその香りは単体での使用のほか、他の香りとのブレンドでも用途の広い香りと言えるでしょう。




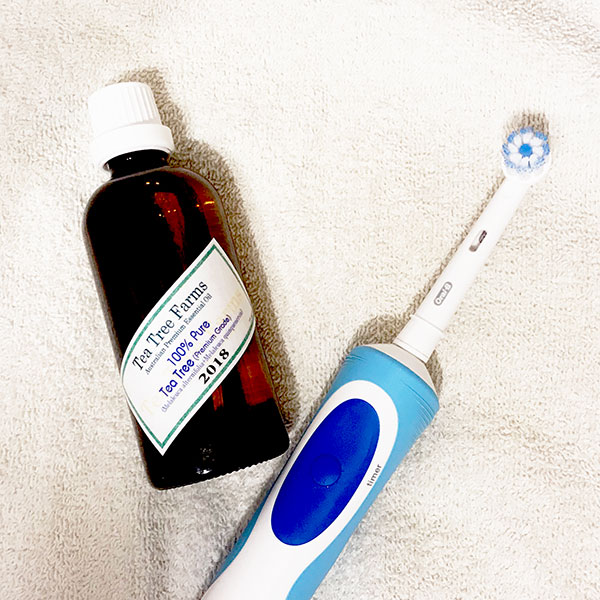



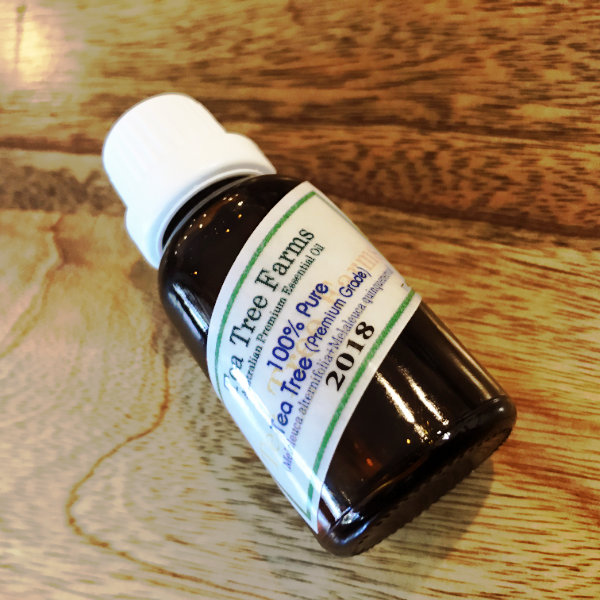


 今回は手前味噌なお話なのですが、
今回は手前味噌なお話なのですが、




 10mlほどの小さな小瓶に入ったエッセンシャルオイル。きっと多くの方が「高かったのよね〜」と、1滴ずつ大切に使っていらっしゃることかと思います。
10mlほどの小さな小瓶に入ったエッセンシャルオイル。きっと多くの方が「高かったのよね〜」と、1滴ずつ大切に使っていらっしゃることかと思います。
