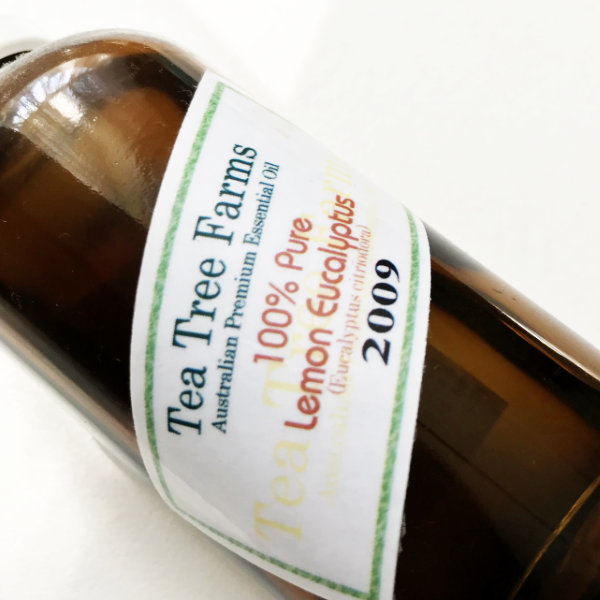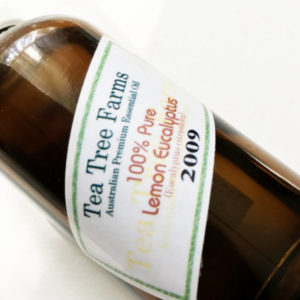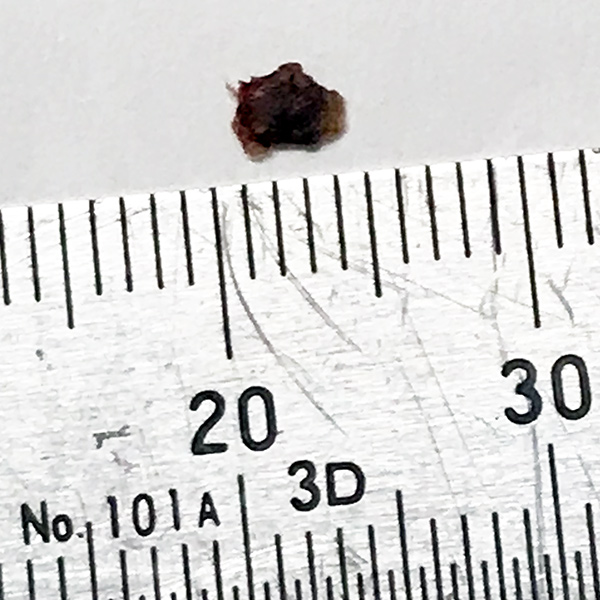乾燥によりダメージなドによりボサボサになった髪。高価なシャンプーやコンディショナーでトリートメントをする方も多いのではないでしょうか? こうした髪は、ホホバオイルを使って簡単にケアすることができるのです。
ホホバオイルをつかった「ヘアパック」。手のひらにゴールデンホホバオイルをとり、両手で広げてから髪全体になじませます。もしフケっぽいような状態であれば、髪と同時に頭皮にもしっかりと馴染ませてみましょう。
短い髪の場合には乾いた髪にそのまま使用しても構いませんし、もし長い髪であれば事前に軽く洗髪してからタオルドライした後に使用すると使いやすいですね。
髪にホホバを入れてから10分ほど置いて、後はいつもどおりにシャンプーをつかって洗い流します。これだけでしっとりした髪に仕上がりますので、コンディショナーは不要になることでしょう。
ホホバをつかった簡単ヘアパック。わずかこれだけでしっとりサラサラの髪を取り戻すことができます。